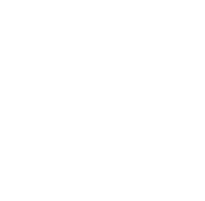第9話 倉敷 舞子「やわらかい炭酸」
コーラは骨が溶けるのよ、と都市伝説を間に受けている母さんはどこまでも滑稽だと思う。舞子はストローに唇を寄せる。コーラの炭酸はすっかり抜けていた。氷と混じって薄まっていても、こびりつくような甘ったるさが舌に残る。
(今、何時だろう)
ファーストフード店で宿題をこなしていた舞子は手を休める。時計を見ると、夕方の五時を回ったところだった。まだ家には帰りたくない。
夕方の店内は学校帰りの学生で賑わっていて騒がしい。バスケ部のジャージを着た女の子や、肩から楽器を下げている吹奏楽部の集団がそれぞれテーブルを囲んで、陣地を築いていた。
それと同じように、帰宅部もまた帰宅部同士でグループを作る。放課後にカラオケやゲームセンターにいくアクティブな帰宅部や、いつまでも空き教室に残って噂話に興じる帰宅部もいた。どのグループとも反りが合わない舞子は誰とも交わらず、喫茶店や図書館、ファーストフード店をその日の気分次第で転々としている。
水っぽくなったコーラをストローでかき混ぜた。もう飲む気がしない。かといって、帰る気もしない。コーラ一つで長居しなくてもいいようになりたいと思った。それには何が必要だろう。たくさん飲みものを注文できるお金か。それとも、こことは別の自分の居場所か。
(……考えても無駄だ。とりあえず問題集もう一回終わらせよう)
再びシャーペンを握って、問題集と向き合った時だった。
「ゲームセンターの中にあるバッティングコーナーでね、ホームラン打ったらベアマックスのキーホルダーもらえるんだよ!」
すぐ隣に座っている栗色の髪をした女の子が声を荒らげている。ファーストフード店で静かにしろ、と注意するのはお門違いだ。けれど勉強中だった舞子は眉を顰めた。
「翼ならきっと打てるよ。キーホルダーゲットしよう」
「よーし、それじゃ行こう!」
翼、と呼ばれた女の子は勢いよく立ち上がった。その元気な背中を追うように、もう一人も慌ててお店を出て行く。これで少しは静かになるか、とため息をついた舞子は、席に残されたバッグを見て苦笑いする。
「こんなに威勢良く忘れ物していくとはね……」
すぐ気づいて戻ってくるだろう、と一度はバッグから目を逸らした舞子は、彼女がなかなかバッグを取りにこないのを気にして小刻みに足を揺らした。
あの元気の良い女の子が、バッグを失くして落ち込んでいるところを想像すると良心が痛む。
「……仕方ない」
舞子は自分の荷物をまとめると、忘れられたバッグを持って彼女の姿を追いかけた。店の外は帰宅するサラリーマンや部活帰りの学生で賑わっている。彼女の姿を探して、あたりを見回す。
「どっちに行ったんだろう。足の速い子だな」
途方にくれていると、車のクラクションが鳴った。黒塗りの高級車が舞子の視界を遮るようにして目の前に停車する。運転席の窓が開き、スーツを着こなした父さんが手を振る。袖口のカフスボタンがきらりと光った。
「やっぱり舞子か」
「もう仕事終わったの?」
「夜にまた会議があるんだけど、一回家に帰ろうと思ってね。送っていくから乗りなさい」
「待ってよ、アタシにも用事があるんだから」
振り返り、左右に伸びる道を見渡したけれど、彼女の姿はどこにもなかった。
「用事ってなんだ。彼氏と待ち合わせでもしてるのか」
「違う。宿題終わらせてただけ」
「もうすぐ青になる。早くしなさい」
「……わかったよ。」
父さんに急かされて、舞子がしぶしぶ後部座席に乗り込むと、車は滑らかに加速して信号が青になったばかりの交差点を突っ走る。
あの子の忘れ物を膝に乗せ、こんなことなら自分で返そうとせずにファーストフード店の店員にバッグを預けてくればよかったと後悔していると、
「舞子」
バックミラー越しに運転席の父さんと目があった。
「いつもあんなところで勉強してるのか。うるさいだろ」
「図書館は混んでるから」
「家じゃ集中できないのか?」
「音楽聞いていい?」
父さんの許可を待たずに、耳にイヤホンをはめる。
父さんの車はレモングラスの芳香剤が強く香っていて、気を紛らしていないと酔いそうだった。この強い香りは、知らない女の人の匂いをごまかすためなんだろうと思う。
舞子は決して父さんの助手席には乗らない。一度、助手席ではぐれたピアスを見つけて以来、そこは不浄な場所になった。そのピアスは運転中に助手席の窓から投げ捨ててやった。その時隣でハンドルを握っていた父さんは、見て見ぬ振りで何も言わなかった。
香りの強い香水をつけたり、ピアスを車に落としていったり、そういうダサいことをする女にかまけている父さんが情けなくて仕方ない。
そしてそんな父さんの挙動に気づかないふりをしている母さんもまた、愚かしかった。
母さんは、帰ってくるかどうかわからない父さんのために毎晩三人分の夕飯を用意する。父さんの席に置かれた夕飯は朝まで放置され、皿が空になっていれば洗い、残された料理は黙って捨てていた。ここ数日は、もくもくと一人分の食事を無駄にする日が続いている。
久しぶりに父さんが夕飯に戻ってきたのをみた母さんは特に驚きもせず、流れ作業のように、
「夕飯なら出してあるわよ」
と答えた。
父さんが時々、夕飯だけ食べに家に戻ってくるのは罪滅ぼしのためだと思う。仕事や女の人との逢瀬に時間を費やしているくせに、一応は家庭人である自覚があるらしい。
そのくせ、一人でちゃっちゃとご飯を食べ終わると、母さんや舞子が食べ終わるのも待たずに食卓を離れ、出かけてしまう。
今夜の夕飯はオニオンスープと鶏肉のバジル炒め、それにサラダが添えられていた。出されている食事は舞子の分しかない。
「母さんは味見してるうちにお腹いっぱいになっちゃったから。夕方にサンドイッチ食べたし」
母さんは食卓テーブルでマグカップにいれたスープを飲みながら、ノートパソコンを開いた。あっという間に食事を終えた父さんは、お皿を下げもしないで、もう外出の準備をしている。また会社に戻るらしい。
いつから、うちの中はこんなにばらばらになったんだろう。舞子はリビングに佇んで、食卓に並ぶ一人分の料理を見下す。
「舞子?」
キーボードを叩いていた母さんがふと目をあげる。
「まだそんなにお腹減ってないからあとで食べる」
舞子は冷蔵庫を開けた。冷えている飲み物は麦茶と野菜ジュースだけだ。
「コーラないの?」
そうたずねると、母さんは冷たく言い捨てる。
「え? 誰も飲まないでしょ、コーラなんて」
「わかった。いいよ」
早々に会話を打ち切ると、食卓に背を向けた。
◇
部屋のドアに背中を預け、ひとりきりになった舞子はため息をつく。余計なことを考えずにすむように、何かに没頭したかった。スポーツなんかどうだろう。団体競技じゃなくて個人競技がいい。家族とさえ連携を取れないのだから、自分はチームワークとは無縁なんだろうと思った。バスケやサッカー、ドッヂボールは無理だろう。それから、野球も。
舞子は床の真ん中に置いてある野球バッグに目をやった。あの子の忘れ物だ。バッグには細かい傷がたくさんついていて、大事に使い込まれていたことがよくわかる。
「持ち主の連絡先がわかるもの、ないかな」
おそるおそるバッグを開ける。中には、野球ボールやグローブ、タオルなど野球をするのに必要最低限のものしかはいっていない。『絶対優勝』と刺繍された手作りのお守りが出てきた時には微笑ましくて笑ってしまった。
舞子は野球ボールを取り出すと、手のひらの中で軽く遊ばせる。
「ドッヂボールの球より小さいのに、意外と重いな」
床に寝そべると、天井に向けてボールを投げた。丸くずしりとした形状が、どこか懐かしい。体を起こすと、棚に飾ってあるドッヂボール大会の優勝メダルが目に入る。
舞子は小学校の頃、ドッヂボール部に所属していた。今では苦手な団体競技だ。
中学でもドッヂボールを続けていたら……と想像して、舞子は首を振る。
ボールを投げたりパスを回したり戦略を立てたり、試合をするのは大好きだった。それなのにやめてしまったのは、部内の空気についていけなかったからだ。試合後の部室で繰り広げられる仲良しごっこには虫酸が走った。
カラオケ行こう。
ドッヂボール部の誰か提案する。すると、誰もがそれに従った。部活中も部活後も、そろって同じことをするのが何より重要であるみたいに。目に見える絆がなければ安心できない。そんな空気が息苦しくてたまらなかった。
舞子は宙高く投げた野球ボールをキャッチした。野球ボールについている薄茶色の土を親指で拭う。
誰かの情熱が詰まった野球バッグから土煙のにおいが溢れ出て、部屋に充満していくようだった。何にも打ち込めずにいる舞子には、そのむせ返るような土臭さが鬱陶しい。一投に全てを懸ける興奮や試合中に浴びる声援、スポーツの楽しさはとうの昔に忘れたはずだ。
はやく、このバッグを持ち主に返してあげたいと思った。そして、この重苦しい荷物から解放されたい。
◇
帰宅部のくせに家に帰ることも、群れて遊ぶことも好まない舞子は、今日も宿題をこなすためにファーストフード店へ向かった。
淡々とこなし続けた問題集はもうボロボロで、学校で習う範囲の勉強はとうに終わっている。
コーラをすすりながら店内を見渡す。バッグを忘れたことに気づいて、彼女がまたこの店に訪れるかもしれない。
忘れ物ならはアタシが預かってるから、と伝えたかった。
「……このお店にはなかったね」
聞き覚えのある声に耳を傾ける。栗色の髪の女の子が店内をうろついていた。
「誰かが自分のバッグだと思って間違えて持って帰っちゃったのかな。ともっち、どうしよう……」
「お財布とか、高いものが入ってなかっただけ、まだよかったね」
「でも、お気に入りのグローブが入ってたんだよ。予備の練習道具はあるけど、やっぱり手になじむのがいいな……」
「元気だして、翼。きっとすぐ見つかるよ」
机に参考書を広げていた舞子は立ち上がった。声をかけようと思い立った時、バッグを失くした彼女が悲しそうに肩を落とす。
「あの……わたし、あなたのカバンを持ち去った人を見ましたよ」
店内にいた女の子が立ち上がった。舞子の体がこわばる。バッグを探しに来ていた女の子たちは、ええっ!? と目を丸くした。
「あなたが席をたった後にすぐ後に、バッグを持って出て行ったの。確か、長い三つ編みの女の子だったと思うけど……もしかして、泥棒だったのかな」
(それって、もしかして……)
舞子は頭を低くして衝立に寄りかかる。後ろに垂れる三つ編みを握りしめると隠すように体の前へ運ぶ。まさか、泥棒だと思われているなんて。
「きっと、バッグを取り違えちゃったんだよ。今頃、探してくれてるんじゃないかな……」
「そうだといいね。それじゃ」
舞子の姿を見たという女の子は店を出て行った。それから数分後、バッグを探していた二人も店を後にする。
舞子は力なく衝立に寄りかかっていた。忘れ物を届けてあげるつもりだったのに。けれどすぐに返せなかったのだから、盗んだと勘違いされても仕方ない。
泥棒がいるなんて……とがっかりしている彼女の背中を思い出すと胃がきりきりした。
「はぁ……泥棒か……」
『私のバッグ、あなたが盗んだの?』
もしそんなことを言われてしまったら。舞子は頭を抱える。直接返す勇気がわかなかった。
(こっそり返す方法はないだろうか……おおごとになる前に。いや、もうおおごとになっているのかもしれない)
コーラを飲みながら項垂れていた舞子は、はっと立ち上がる。
あの子が野球部に所属しているのは間違いない。それなら、この町で野球をやっているところを順番に探せばいい。練習場にそっとバッグを置いておけば、彼女に気付いてもらえるはずだ。
◇
バッグと自転車を取りに帰ると、家には誰もいなかった。テーブルの上には汚れた空っぽの皿が出しっぱなしになっている。いつの間にか父さんがご飯だけ食べに寄ったらしい。痕跡だけ残していく父さんは幽霊のようだった。それを黙って片付ける母さんも、二人とも不気味だ。
野球バッグを自転車の荷台に乗せると、ペダルに足をかける。立ち漕ぎで、左右を乱暴に踏みつけながら走る。家からぐんぐん遠ざかると気持ちよかった。どうせ夜には帰らなければいけない。けれどそれまでは、家のことなんて忘れてしまいたかった。
ファーストフード店の近くにあるグラウンドで、野球をしている集団を見つけた舞子は自転車を近くに寄せる。そこにいるプレイヤーは男の子ばかりだった。
(野球やってる女の子って全然いないんだな)
ベンチのそばに、一人だけ女の子がいる。ヘルメットから、一本にまとめた長い黒髪が垂れている。凛々しい眼差しで打席を見つめていた。馴れ合いを許さないような鋭い姿勢に少しだけ心惹かれた。
(でも、アタシが探している子は、黒髪じゃなくて、もっと淡い茶髪だった)
舞子はグラウンドに背を向けると、次のグラウンドに向かってペダルを深くふみこんだ。
自転車の車輪が優しい音を立て、柔らかい風が耳をかすめていく。
次はどこに向かおう。あの子はどこにいるだろう。自転車で風を感じるのが気持ちよくて、このまま隣町まで行ってしまいたかったけれど、知らない場所で一人きりになることを思うと心細い。
勢いづいた自転車にまたがって道を下っていると、遊歩道の茂みから人が飛び出した。舞子は即座にブレーキを握る。自転車は道に黒いタイヤ痕を残して急停止した。
「申し訳ないにゃ! つい前しか見てなくてにゃ……」
首から大きなカメラをぶら下げた女の子は、早口で謝罪しながら深々と頭を下げた。ヘアバンドのように額の上にメガネをかけている。
「普通、人は茂みからでてこないでしょ」
「サッカーボールを探してたんだにゃ」
「サッカー部のマネージャーか何か?」
「ちがうちがう、ワタシは新聞部!」
「新聞部がなんでサッカーボールを?」
「サッカーの試合、よく取材にいくんだけど、いつもお世話になっててにゃ。困った時はお互い様だにゃ。そっちも、もし困ったことがあったらワタシを頼って欲しいにゃ。特ダネスクープから噂話の真相まで、なんでも知ってるにゃ♪」
彼女が自信満々に微笑んだ時、活動的なショートヘアーの毛先が揺れた。
「聞きたいことがあるんだけどいい?」
「もちろん!」
「この町で、野球の練習場を……いや、人を探してるんだ。野球をやってる中学生の女の子なんだけど。たぶん、どこかの練習場にいると思う」
「野球をやってる中学生の女の子? ってことはシニアリーグの練習場所かにゃ……」
新聞部の彼女はポケットからスマホを取り出すと、指先で素早く操作する。
「思い当たるのはこの三箇所だにゃ」
そのうち二つはすでに回った場所だった。残るもう一つの球場も、ここからそう遠くない場所にある。
「ありがとう」
「いえいえ。それじゃ〜にゃ〜」
彼女に別れを告げると、舞子はまた自転車を走らせた。広々としたグラウンドに近づくと、運動部特有の地鳴りのように響く声が聞こえた。声出ししながらの練習の真っ最中だった。
自転車にまたがったまま地面につま先をつけると、グラウンドを見渡す。
「……あの子だ」
男の子に混ざって、栗色の髪の女の子がバットを振っていた。借り物のバットでは調子がでないのか、空振りを連発している。
舞子は自転車を止めると、練習場に忍び寄る。グラウンドの外には誰もいない。他人目を気にしながらフェンスのそばにバッグを置く。
(よし、これでもう大丈夫だ)
長く抱えてこんでいた重荷を降ろし、すっきりした気分でその場を離れた時だった。
「翼、がんばれーっ!!」
遠くから、そう叫ぶ声が聞こえた。その声に驚いて振り返る。フェンスの外に、制服姿の女の子が立っていた。彼女はフェンスに指をかけ、たった一人で選手を応援しているようだった。
打席に立つ少女はボールに集中しているらしく、こちらには背を向けたままで彼女の応援には一切答えない。
(一人で応援するのって、寂しくないんだろうか)
舞子もフェンスに指をかけてみる。とても越えられそうにない頑丈な壁だ。がんばれ、とフェンスの外にいる女の子がもう一度声をあげる。一生懸命に声援を送る彼女は、遠目にもどこか生き生きして見えた。
選手じゃなくても、ここには彼女の居場所があるのかもしれないと思った。舞子は靴底で、ざらついた地面の土を撫でた。ここはスポーツをしない制服姿の女子には優しくない場所だ。けれど、そんなことは関係ないんだ。
舞子は踵を返すとその場を立ち去った。
ゆるゆるとペダルをこぎながら帰路につく。自転車の影が斜めに伸びる。車輪が回る音が涼しい。
あの子の明るい声援だけは妙に鼓膜に焼きついて離れなかった。高いフェンスの外で、ひっそりと応援を続ける彼女は一人ぼっちなんかじゃなかった。フェンスに阻まれていても、二人の気持ちが通じ合っているように見えるのが不思議だった。
一人でいても一人じゃない。そんな居場所があったら、それはなんだか心地よさそうだと思う。
◇
帰宅すると、母さんが昔のアルバムを見ていた。舞子がドッヂボールをやっている頃の写真が目に入る。
「おかえりなさい。今、小学校の頃のアルバムを見てたんだけど……あなたは父さんに似て、昔からなんでもできたわね。一緒に見る?」
「昔の写真なんて、興味ないよ」
舞子は母さんの真横を通り過ぎるとキッチンに向かい冷蔵庫を開けた。ウーロン茶の隣に真っ赤な缶が並んでいる。
「あ」
よく冷えていたコーラが一本入っていた。舞子はリビングでアルバムをめくる母さんの背中を一瞥する。
母さんのことを好きにはなれないけど。
母さんも、居心地の良い場所が欲しいだけなのかもしれない。嘘をついて、気づかないふりをしてでも。みんなばらばらに行動して、離れ離れでいても。それでもここは、家族が帰る場所だ。
部屋に戻ると、コーラを飲みながら参考書を開いた。シャーペンのペン先がノートに擦れてだんだん丸くなっていく。作業的に問題集の空欄を埋め続けていた舞子は、腕を休めるとコーラを一口含んだ。
炭酸が舌の上でぱちぱち弾け、喉の奥へ沁みていく。コーラの甘みに刺激されて余計にお腹が減る。時計を見ると、もう夕飯の時間だ。
たまにはみんなでご飯を食べるのもいいだろうか、と悩みながら舞子はシャーペンを転がした。