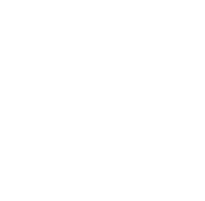第1話 有原 翼「最後の試合」
うっすらと曇っていた空に白球が飛んでいく。その打球は曇り空を突き破るような勢いでぐんぐん伸びていく。割れるような歓声が起こり、球場が揺れた。ホームランを打った翼を祝福するみたいに、空が晴れていく。
「翼、ないすー!」
笑顔でホームに帰ってきた翼はともっちに向かって手を振ってから、チームメイトのもとに戻る。
みんなから激励を受けた翼は、次の打席に立つ男子と目を合わせた。
「くそー、翼いい球打つなー」
不満そうにつぶやく彼に、翼が笑いかける。
「悔しい?」
「別に! こっから俺の出番だな。有原はそこで見てろ」
翼は彼の背中を軽くこづいて送り出した後、ベンチに腰掛けた。コーチが翼に微笑みかける。
「有原、ここぞって時にいいの打ったな。次はあいつか」
「絶対決めてくれますよ」
翼はまっすぐな目で彼の背中を見つめる。練習中は追い越すのに必死だった彼の背中が、試合中になるととても頼もしく見えた。彼はチームの主将だ。
八月の太陽が打席を照らしている。暑い日差しが球場を照らし、土の焼けるような匂いが選手たちの鼻をつく。
翼たちが挑んでいる試合は、リトルシニア日本選手権の決勝戦だった。今日この試合で全国556チームの頂点が決まる。翼たち三年生にとっては、これが中学生活最後の公式戦だった。
バットを握った主将がベンチの方を振り返る。
「 」
声は聞こえなかったけれど、翼には彼が何といったかはっきり読み取れた。試合の前日、昨日口ずさんだ言葉と同じだったからだ。
◇
「絶対勝つぞー!」
「おー!」
最後の練習を終えたチームは円陣を組んだ後、いつもどおりに騒ぎあい、ふざけ合いながら解散した。
「明日は中学最後の大事な試合なんだから、今日は無理するなよ」
コーチにはそう忠告されていたけれど、明日がいよいよ決勝戦かと思うと翼は落ち着かなかった。
「ちょっと外周走って、体慣らしてから帰ります!」
そういう翼につられて、チームの主将が「じゃあ俺も」と答えた。
「残るの?」
「競う相手がいる方が調子でるだろ。ほら置いてくぞ」
彼は翼より早くスタートを切って走り出す。慌てて翼が横に並んだ。
西に落ちた太陽が、灰色のコンクリートをオレンジ色に焼いていた。道にできた影が自分の身長よりも長く、不気味に伸びる。
「調子はどう?」
彼が翼に尋ねた。
「まあまあかな」
「不安とかないの?」
軽くちゃかすように問いかける。
「不安、うーん」
翼は少しだけ空を仰いだ後、すっと前を向く。
「これは不安じゃなくて緊張だよ。多分。明日の試合は、中学生活の集大成だから」
「そうだな。……この三年間、有原がどのくらいがんばってたか、俺はっ、」
ぐしゃ、と彼の足元で嫌な音がした。おそるおそる足をあげると、大きなカメムシが潰れていた。
「わっ、カメムシだ」
「……」
彼はわずかに頬を赤らめて、翼から顔を背けた。
二人は横並びになって、同じペースでグラウンドの外周を走りつづける。
「こうやって走ってると、入部したばっかりのこと思い出すな」
ふと隣に並ぶ翼の影に目を落とした。それは彼の影より拳三つ分、離れた場所にある。
野球部の主将となる彼と翼がはじめて出会ったのは中学一年生の春のことだった。
彼が窓際の席に座りながら眠気に抗って頭をもたげている時、ふいに鼻先を柔らかい絹糸のようなものにくすぐられた。目をこすると、目の前に座っている女の子の艶やかな髪が、窓から入る風にそよりと吹かれて揺れていた。
素直そうな子だな、と思った。けれどその第一印象はすぐに更新された。彼女が、数学の教科書を開いているふりをしながら「野球のイメージトレーニング方法」という本を読んでいるのを見つけてしまったからだ。
野球が好きな女の子に出会えただけで嬉しかった。その時はまさか、翼がプレイヤーだとは思いもしなかった。
話しかけてみたいけど、何て声をかけよう。そう二の足を踏んでいる彼に、話しかけたのは翼の方だった。その時は思わず心臓が飛び跳ねた。
「君、野球やるの!? 軟式? 硬式?」
汚れた野球バッグを見て翼は目を輝かせた。
「硬式だけど……」
「じゃあリトルリーグの人なんだね! やった! 同じだ」
「もしかしてマネージャー? 野球好きなの?」
「マネージャーじゃなくて、選手だよ。よろしくね」
翼が強くそう言い切るのを聞いて、そっけなく「よろしく」と答えた。翼はその後も他のチームメイトからマネージャーだと勘違いされ、そのたび何度も「選手です」と胸を張って答えた。はいはいマネージャーも選手と一緒に戦ってるもんね仲間だもんね、と適当に受け取る部員もいたけれど、翼は決してめげなかった。外野の声を、彼女は努力と実力で打ち消してきた。中学生男子の体力を基準にして作られた練習メニューを懸命にこなし、「いつ辞めるだろうね?」とニヤつく男子たちを追い越して、同学年のエースである彼の横を走り続けた。
入部して三ヶ月たった頃。はじめてコーチが公式戦に抜擢した一年生は彼自身と翼だけだった。それ以来、二人は三年になった今でも、二人でチームを引っ張っている。
マネージャーじゃなくて、選手だよ。そう宣言した時に見せた屈託ない翼の笑顔を、彼は今でも覚えている。
「なんだかあっという間だな」
思わず、ため息混じりにつぶいた。
外周を終えた二人は一緒に、グラウンドのベンチに腰を下ろした。
翼は誰も立っていない打席を見つめて、絶対勝とう、と答えた。それぞれが、特別な想いを持って最後の試合に挑むことは確かで、翼の「勝とう」にもそれが込められているに違いなかった。
「俺、負けないよ」
膝の上で拳を強く握る。
「その意気だよ」
「……試合にも勝つし、有原にも負けない」
翼は黙り込んだ。女子だからね、と言われるのが悔しくて誰よりもバットをたくさん振り続けた日のことや、マネージャーと間違えられてもめげなかった日のことが頭をよぎった。彼はちゃんと私をライバルだと認めてくれてたんだ。私も負けない、と言い返したかったけれど、それは明日の試合に勝ってから言おうと思った。
翼はそっと生唾を飲み込んでから、顔を上げた。
「優勝したら、チーム代表スピーチとかするのかな? プロ野球のヒーローインタビューみたいに。ねえ、優勝したらなんていう?」
「えーなんだろう。有原はなんていう?」
「うーん、そうだなぁ。これからも野球続けていきます!」
「ありきたり!」
「いいでしょ、球場で叫びたいことなんてそれしかないから」
「俺も! 野球続けるぞー!」
そしてベンチから立ち上がると、誰もいない球場に向かって叫んだ。
「続けるぞー!」
おどけた調子で翼が続いた。二人の声は、踏み固められたグラウンドの土に吸い込まれて、消えた。
◇
俺、負けないよ。
そう囁いた主将は、予言どおりホームランを放った。
七回裏。ホームベースをしっかり踏みしめて、膝を落として体全体でガッツポーズを決めた。手にした勝利を放しはしない、とでもいうかのように両手の拳を強く握る。
涙目で喜ぶ翼とハイタッチしようとするも、押し寄せた仲間たちのせいでもみくちゃになる。有原、と翼の名を呼んだ。翼はにっこりとこちらに向かって親指を立てた。
試合終了のサイレンが鳴り、決勝戦は翼たちの勝利で幕を閉じた。
閉会式を終えると、チームメイトはそれぞれ友達や家族のもとへ散っていく。
翼は主将の姿を探す。ともっちに勝利の報告をしに行く前に、一言宣言したいことがあった。
「コーチ、ホームランのお祝いが言いたいんですけど……」
「あー、あいつならすぐ外にいると思うよ」
コーチは少し気まずそうに眉をひそめる。翼はお礼を言って、コーチが指差した方へかけていった。
彼の姿はすぐに見つかった。スーツ姿の大人と話し込んでいる。
「君、打率すごいね。高校はもうどこか考えてる? うちの高校にきたらもっと化けるよ。甲子園で活躍すること間違い無しだから」
高校野球のスカウトだ。彼は舞い上がっているようで、面倒くさそうに頷きながらも、輝いた目でスカウトの大人を見つめている。
「有原……」
翼の存在に気づいたようで、はにかみながら手を振った。翼が駆け寄ろうとするよりも早く、また別の大人が彼に声をかける。
「今日の試合おつかれさま。よかったらうちに来てよ。またあとでちゃんと連絡するね」
「うち以外からもスカウトくるだろうけど、頼むよ」
翼はその場で立ちすくんだ。スカウトに囲まれている彼を見ていると、数時間前同じ試合に出て、一緒に活躍したことが信じられなかった。私もチームメイトなのに。甲子園に出られないことはわかっていた。けれど、だからどうってこともなかった。今初めて、甲子園の大きさと遠さを感じた。
チームに入部したばかりのことが頭をよぎる。
『君、もしかしてマネージャー?』
『そんな細い腕で無理しなくてもいいよ。どうせそんなに体力もないだろうし』
『レギュラーにはなれないと思うよ?』
悔しいこともあったけれど、全部乗り越えて優勝まできた。けれど、スカウトの大人に囲まれている彼と自分の間にはどうしようもない壁があるらしい。
「翼〜、おつかれさま」
その時、ともっちが翼の肩を叩いた。
「翼すごくかっこよかったよ。大活躍だったね」
「応援してくれてありがとう。お腹減ったよー」
「じゃあ今日は何かおいしいもの食べようよ〜」
ともっちに誘われて踵を返し、外に止めてあった自転車にまたがった時、
「有原!」
遠くから彼が駆けてきた。翼は自転車のペダルに片足を乗せたまま、ブレーキを軽く握る。よほどの勢いで追いかけてきたらしい。肩を弾ませて、荒い呼吸を繰り返す。
「有原! 俺たち勝ったな」
「そうだね。いい試合だったね」
ええと……と言葉を詰まらせながら、翼にこう言った。
「なんていうか……おつかれさま」
おつかれさま。優しい労いの言葉が、ちくりと胸に刺さって沁みた。まるで野球とさよならしなければいけないみたいだ。その言葉に他意がないことはわかっていた。けれどその顔を直視していられなかった。
「ありがとう」
それじゃ、と手を振って、翼はともっちと並んで球場を後にした。明日から、練習のない毎日が始まる。
◇
放課後ってすごく長い、と翼は空き教室からぼんやりとグラウンドを眺めた。陸上部の練習に混じってこようか、とため息をつく。
野球がやりたいな、とつぶやきながら、窓にある落下防止用のポールを握る。冷たい感触。十二月頃の練習を思い出す。冬のバットは冷たかった。
あの優勝試合から、もう一ヶ月が経とうとしている。翼は未だに、シニアリーグに代わる何かを見つけられずにいた。
「翼、先生が呼んでるよ」
ともっちの知らせを受けて職員室に足を運ぶ。担任の先生が、気だるげに書類をひらひらさせた。
「陸上の強豪校から推薦来てるぞ。どうする?」
「陸上は……」
「有原が野球が好きなのは先生もよくわかってるけど、こればっかりはなぁ」
「……」
体の前で手を組んでいると、職員室の扉が開いた。
「失礼しまーす」
彼だ。翼はとっさに目をそむけた。けれど、顔を合わせていなくても、その場の会話は漏れ聞こえてしまう。
「よかったなー、おめでとう。どこの推薦受けるか決まったか? どこも甲子園常連校だもんな」
陽気な先生の声とは裏腹に、小声で「この学校……受けたいです」と自信なさそうに書類をさしだした。
「どうする、有原」
そのすぐそばで、担任の先生が翼に問う。
「……とにかく、陸上の推薦は受けません。失礼します」
翼は彼に背を向けたまま職員室を出ようとした。扉を閉めようとした瞬間、視線がぶつかる。
合格おめでとう、の一言くらい伝えようか。翼が口を開いた時、先生が彼の肩を叩きながら「おめでとう!」と叫んだ。祝福を受けた彼は、目を細めて笑っている。
野球の推薦で高校が決まった彼と、陸上部の推薦しかこない自分。互いをライバルだと思って練習してきた日々を思い出しそうになり、翼は慌てて職員室の扉を閉めた。
落ち込んでたって仕方がない、私は私で、彼は彼で進んでいかないといけないんだから。そんなことはわかってるけど。
「翼」
職員室の前で待っていてくれたともっちが微笑んだ。
「ともっち、待っててくれたの?」
「当たり前だよ。私はいつだって、翼のこと応援してるからね」
「ありがとう」
優勝した最後の試合でも、一番大きな声で翼を応援してくれたのはともっちだった。励ましてくれる友達がいるんだからがんばらないと。翼はともっちに微笑み返した。でも、何をがんばるんだろう。がんばる、という言葉だけがむくむく大きくなって、頭の中を圧迫していた。
玄関に、踵の磨り減った靴が置いてあった。大学に通う姉のものだ。翼のものより少し大きい。こんな時間に、姉が家にいるのは珍しい。
リビングでは、大学生の姉がお菓子をつまみながら野球雑誌を読んでいた。
ただいま、とつぶやくと、「おー、おかえり。翼も食べる?」と勧められた。
「食べる」
翼はソファーに腰掛け、姉と一緒にお菓子をつまむ。野球雑誌をめくる音と、お菓子のビニール袋を開ける乾いた音だけが、かさかさと部屋に響いた。
「姉ちゃんそれ大学野球の雑誌?」
「ううん、高校野球だよ。甲子園。もう試合は全部終わっちゃったけどね」
「甲子園」
そう口ずさむだけで、なぜだかちくりと胸が痛んだ。
「そっか、翼はシニアリーグの試合があったから試合見てないでしょ。見る? 録画してあるよ。今年は本当に見ごたえのあるのが多くて。楽しいよ」
姉はそういうと、嬉々としてテレビの電源をつけた。翼が口を挟む間もなく、テレビではこの夏行われていた試合が流れ始める。
ド派手に奏でられる吹奏楽部の演奏。制服姿で大きな旗を振る応援団。まるでお祭りのようだ。それら観衆の真ん中に立つ、白いユニフォームの選手たち。奥歯を食いしばり、一球一球に祈りを込めるような顔で投げるピッチャー。一瞬の気の緩みすら許さない鋭い瞳で、白球を見つめているバッター。中腰になり、いつでも全力で走り出せるよう構え続けているランナー。
一投、一打で会場が狂喜と落胆に沸く。試合終了後も、しばらく歓声が途切れることはない。勝った方は何もかもかなぐり捨てて喚きながら抱き合い、負けた方は頽れる。
勝っても負けても涙が出るような熱い試合だった。
翼は静かに息を飲んだ。
「私も出たいな、こういう試合に」
気づけば、独り言のようにつぶやいていた。
「出なよ」
姉はお菓子の袋をたたみながら、なんてことない風に答えた。
「でも、甲子園に女子は出られないよ」
「今はね。でも、この先どうなるかは誰にもわからないよ。翼が変えていけばいいんじゃない?」
テレビ画面には甲子園球場の空が映っていた。試合が終わると、さっきまで薄暗かった空が嘘のように晴れ始める。翼は、自分が最後の試合に放ったホームランのことを思い出した。白球が遠く伸びるほど威力が増しているように感じた。まだ落ちない、まだまだ伸びる。ホームランを打った時は塁を踏む足も軽やかで、たとえどんな荒地でもどこまでだって走り抜けられるような気がした。その時の感覚が、じわりとよみがえってきた。一発逆転ホームラン、とまではいかなくても、試合の結果は、自分の手で変えられるはずだ。
「……お姉ちゃん、他の試合も見たいな。録画してる?」
「いっぱいあるよ〜、どれがいいかな?」
姉は嬉々とした顔で前のめりになって、録画記録を漁り始める。その夜、二人は両親に「いい加減早く寝なさい」と怒られるまで試合を見続けた。ベッドに入っても、テレビで見た試合の興奮が忘れられなくて、翼はその晩寝付けなかった。
翌朝、翼は遅刻ギリギリで教室に滑り込んだ。チャイムが鳴り終わると同時に着席。セーフ、と息をつくと、近くの席のともっちが翼に手を振った。
「翼、おはよ〜」
「おはよう、ともっち。あっ、ともっちに借りてたノート返さなきゃ。ありがとう」
「ううん、ノートくらいなんでもないよ〜。あれ、翼、少しだけ目が充血してるよ?」
「大丈夫だよ。昨日、ちょっと夜更かししちゃっただけだから」
「でも、なんだかすっきりした顔してるね」
「ちょっと眠たいけどね」
翼は苦笑いした。何も言わなくても、ともっちにはすべてお見通しだ。
軽く目をこすっていると、誰かがおもいきり教室のドアを開いた。
「先生まだきてない? セーフ。よかったー」
彼だ。新しい野球バッグをさげて、教室に飛び込んでくる。あの野球バッグは、新しい高校のものだろうか。入学前から練習が始まっているのかもしれない。
じっとバッグを見つめていると、その視線に気づいたようで、わざと翼に背を向けるようにして着席した。
翼は頬杖をつく。切磋琢磨してきた三年間が、こんな形で終わっていくのはなんだか寂しかった。
眠そうに揺れるその後頭部に目をやる。彼は、高校野球期待の新人である以前に、私のライバルだ。
数学の授業中、翼はノートに意味のない図形をあれこれ落書きしながら、胸の内で一人唸る。卒業前に言ってやりたいことがあるのに、うまく言葉にできなかった。
それはまるで通り魔のようだったと思う。理科室に移動している間のことだ。
翼は彼の背後に素早く近寄ると、すれ違いざま、叩きつけるようにこう言った。
「今日の放課後、野球道具持ってグラウンドにきて」
「えっ?」
「きてね。今日だからね」
驚いている彼を無視して、翼はそのまま廊下を歩き去った。
グラウンドにはひと気がなく、二、三日整備を怠っただけで、雑草が生え始めていた。今はテスト期間中で、どの部活もおやすみになっているせいだ。
約束通りに彼が現れた時、翼はすでに打席に立って待っていた。
「有原?」
不思議そうにしている彼に向かって、翼はバットを突き出した。
「私と勝負して」
「えっ。勝負って、どんな?」
「三球勝負。君が投げる球で、一球でも私がホームランを打ったら私の勝ち。もし三球ともストライクだったら、君の勝ち」
「すごいシンプルなルールだな」
「でしょ」
「おもしろそーじゃん」
彼はカバンからキャップとグローブを取り出した。翼と、こういう直接対決をするのは初めてだった。互いに打ったホームランやヒットの数を競うことはあっても、マウンドで翼と対峙したことはない。打席に立つ翼を見て、口元を引き締める。
翼の顔を見るのは久しぶりだった。彼も翼に話したいことがあったのに、あの試合で優勝して以来、まともに顔を見られずにいた。野球を通じて彼女に憧れ、試合や練習の中で絆を深めた。自分だけが野球の推薦入学が決まった時、翼との繋がりが消えたようで、このまま一言も話さずに卒業するのかもしれない、と思っていた。
彼は、迷いのない足取りでマウンドを踏みしめる。
「『俺は打者だからピッチング下手で』、みたいな言い訳はなしだからね!」
「そんなかっこ悪いこといわねーよ。これでも一通り練習してんだから。小学校時代は豪速球のピッチャーと恐れられもともとはピッチャー志望でチームに、それで、」
「わかった。とにかく、本気で投げてくれるってことだね」
翼は彼の自己アピールを遮って、手慣らしにバットの頭を振った。
「当然」
彼はボールを磨くと、手のひらになじませるように軽く握った。片足を軽く上げ、肩からボールを振りかざす。
うなるような風音とともに、ボールは翼のバットの下をすり抜けた。そして、背後に設置した練習用ネットの中に落ちる。
「おおー」
力投を目の当たりにした翼は、ヘルメットをかぶりなおした。
「まあ、こんなもんだよ」
「初球は様子見しただけだよ。ほら、はやく二投目」
翼は背筋を伸ばすと、バットを構えた。
「はいはい」
肩を伸ばし、ゆるいストレッチをしてから投球フォームに入った。先ほどと同じように片足を上げ、右腕を振りかざす。
かんっ、と小気味好い音が鳴る。翼のバットがボールの中心を捉えた。白球が綺麗な放物線を描いて、放課後の空に昇っていく。
「え……っ」
口をぽかんと開いたまま、ボールの行方を目で追う。
「ホームランだね! 私の勝ち!」
翼が得意げにそう言い放った瞬間、パリン……、と悲しげな音がした。
翼のホームランは校舎の四階に直撃し、窓ガラスに穴を開けた。
「「あっ……」」
二人の声が重なった。
呆然としたまま、打席にいる翼の方をゆっくり振り返る。
「まさか有原、窓ガラス……」
「あ、あはは……」
翼は苦笑した後、ヘルメットを脱いで、まっすぐに彼を見つめた。
「私、君に言いたい事あるんだ」
「な、なんだよ」
「高校合格おめでとう。私も高校で男子に負けない野球チーム作るから、君も絶対甲子園に行ってよね」
「有原も続けるんだな」
「当たり前だよ」
翼がにっこり笑うのを見て、翼と初めて出会った時の頃を思い出した。自然と頬が熱くなる。ちょうど夕暮れ時でよかった、照れているのがバレずにすむ、と苦笑しながら、静かに呼吸を整えて、
「俺も翼に言いたい事が、」
「こらーーーーー! ガラス割ったの誰だ!!」
その時、四階の窓から先生が顔を出して叫んだ。先生の手には、翼の放ったホームランボールが握られていた。
「うわっ、やべ」
「はやく逃げよう!」
「えっ、逃げるの?」
「私たちが割ったってバレたら絶対怒られるよ!」
「ちょっ、有原、足速っ!」
「捕まった方が犯人だからね!」
「いや俺ら同罪でしょ!?」
先を走っていた翼が足を止め、いたずらっぽく笑った。そしてゆっくり振り返った瞬間、翼の髪がふわりと揺れて夕暮れの光を反射する。その一瞬だけ、時間が遅くなったように感じた。有原、と彼が彼女を呼ぼうとした時、翼はするりと踵を返し、前を向く。華奢な背中がオレンジ色に輝いて見える。小さく吐息をこぼした。前を向いて進む翼の背中はいつだって眩しい。ぐっと足に力を入れて翼に追いつき、翼のすぐ隣を並んで走った。
「もっと走ろ!」
翼は息を弾ませながら叫んだ。
「どこまで?」
「知らない!」
隣を走っていた翼が一歩前に出る。加速する翼の背を追い越すために、彼もまたスピードを上げる。
翼は彼の足音を聞きながら、これからも私たちは走っていくんだと思った。全く同じ道ではないにしても、似たような道を、それぞれ違う方法で進んでいくんだ。
下り坂に差しかかった。あらがえない重力に引かれて、二人の足並みはどんどん速くなっていった。