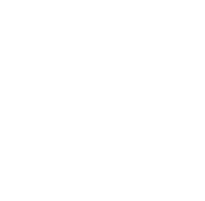第3話 野崎 夕姫「私には効かないおまじない」
「ねえ夕姫。緊張を解く方法教えてあげようか?」
美砂にいきなり話しかけられ、夕姫の肩が震えた。
「ど、どんな方法ですか……?」
美砂は前歯を見せて笑いながら、夕姫の目の前に飴玉を差し出す。
「甘いものを食べること。ただし、試合が始まる前に食べ終えてね!」
「本当ですか? 飴を食べたら緊張しない……?」
「……まあ、おまじないみたいなものだよ! 信じれば、嘘も予言に変わるのです」
「ありがとうございます」
美砂からもらった飴玉の封を開け、夕姫は壊れ物でも扱うように、大切に口の中に含んだ。
「今日は乙女座が一位だから、夕姫にも活躍するチャンスあるかもよ?」
ユニフォームに着替えた美砂は、夕姫に背を向けてコートに向かう。夕姫も念のためユニフォームに着替え、数分遅れて、美砂たちの後に続いた。
今日は他校のバスケ部との練習試合だ。
コートの真ん中に立つ審判が、バスケットボールを宙に投げた。ジャンプボールに成功したのは、敵の選手だ。試合は相手チームの攻撃で幕を開けた。
十人分のバスケットシューズが体育館の床に擦れて、キュッと音を立てる。それを聞くたびに気持ちが引き締まった。
みんな、すごい。心の中でそうつぶやいた夕姫は自分の唇に指を添える。食べ終えたメロン飴の味が、まだほのかに残っていた。
チームメイトが強引なカッティングでパスを横取りしていく。審判に隠れて敵のユニフォームを引っ張りシュートの邪魔をしている。
仲間の試合を見ながら、夕姫は息を飲む。自分がコートに立った時、同じようにプレイできる自信がなかった。
せめて声出しくらいはがんばろうとベンチから声援を送る。練習試合の相手は公式戦でもよくあたるライバル校だ。今は二十八対三十二で夕姫たちの方がリードしていた。
ピッ、と審判の笛が鳴る。
相手チームの選手が体当たりしてきて、選手が二人、転倒してしまったのだ。
このくらいのことは試合中によくおきる。大した怪我ではなかったけれど、監督は気難しそうに腕を組んだ。
「野崎、行けるか」
「えっ!? わ、私ですか?」
「行けるか?」
「はっ、はい!」
準レギュラーの夕姫は試合にでる機会がすくない。この試合は貴重な活躍の場だった。
夕姫は首にかけていたタオルをおいてコートに入った。練習試合前にシュートやドリブルの練習をしていたから、体はもう十分に温まっている。
「あ、選手交代だ。あの人すごい背高いね。シュートばんばん入れてきそう」
ギャラリーの声を耳にして、夕姫は体がこわばった。期待されると、肩に余計な力が入る。バスケットボールのドリブル音よりも、自分の心臓の音の方が大きく聞こえた。
「夕姫!」
ゴールの近くにいた夕姫のもとにパスが回ってきた。またとないチャンスだ。相手選手がボールを奪おうと手を伸ばす。敵をドリブルでかわしてシュート体勢に入った時、急に腕が重くなる。相手選手の鋭い眼光を目の端に捉え、息が止まった。
――私のシュートが入ってくれたら。
夕姫が祈るような気持ちで放ったボールは、リングに当たって跳ね返った。ハズレだ。
「リバウンド!」
チームメイトの叫び声にはっとして、夕姫は慌てて高く跳ぶ。けれどボールは、夕姫より背の低い相手選手に取られてしまった。すぐにディフェンスに回ろうとボールを持つ選手の後を追う。けれど全く追いつけず、試合の主導権を相手に奪われてしまった。
緊張しないおまじないは、まるで効かなかった。
「野崎」
監督は、黙ってベンチを指し示す。
チャンスを無駄にした夕姫はその後すぐ他の準レギュラー選手と交代になり、またベンチを温めることになった。
「あの人、すぐ交代させられちゃったね。身長高いのにもったいないな」
ギャラリーの声は率直だった。肩身の狭い思いがして、自然と肩が丸くなる。監督が夕姫を冷たく一瞥した。
その身長は武器になるぞ。
バスケ部に入部したての頃、監督からそう言われて、夕姫は胸が熱くなった。今までコンプレックスだった身長の高さを、ここでなら強みにできるかもしれないと思った。けれど、未だこの身長は「目立って恥ずかしい」だけのお荷物だ。そして監督は、いつまでも力を発揮できない夕姫に、苛立ちを募らせている。
練習試合の結果は勝ちだった。お疲れ様、と明るく肩をたたき合う友達の中で、夕姫の顔だけが引きつる。
ユニフォームを脱いだ夕姫は、水飲み場の鏡を見てため息をついた。自信のなさが瞳に出ていた。鏡に指を当てる。そこに映る不安げな瞳を撫で、
(大丈夫……せめて、笑おう?)
口角を上げ、笑顔を作る。鏡から指を離す。そこに映る自分は、自信満々とはいかないものの、穏やかな笑顔を浮かべている。
たとえ自信がでなくても、自信のない顔をするのはやめたかった。
シュートが入ってくれたら、と祈るより、私のシュートは入るんだ、という気持ちでいたい。そうじゃなければ、試合では必ず負けてしまう。
けれど、夕姫はどうしても、そうなれなかった。
ポケットから出てきた飴玉の包み紙を捨てる。緊張しないために必要なのは甘いお菓子なんかじゃない。
◇
「夕姫、今日あんまり元気ないね?」
美砂が怒鳴るように尋ねた。カラオケボックスの中では、声を張らないと隣に座っている相手との会話も困難だ。マイクを片手に飛び跳ねているチームメイトたちを見ていると、とても練習試合の後だとは思えなかった。
「今日の練習試合のことを考えていまして」
「えー、勝ったんだから別によくない?」
「でも、私せっかくチャンスをもらえたのに、シュート一本もいれられなかったので……」
「夕姫は身長もあるし、バスケ向きの体してるのにね」
「どうしたら、もっと上手になれるんでしょう……」
「夕姫は下手じゃないよ。別に。練習の時はできてるのに、試合になるとなぜかできなくなるだけで」
「うーん……」
「あたしは今日、隣で男子が試合してたからはりきっちゃった!」
美砂が叫んだ時、ちょうど曲が終わり、部屋が静まり返る。
「美砂ってうちのバスケ部の男が好きなの? 矢島?」
マイクを置いた友達が、美砂に詰め寄った。
「違うよ!」
「でも男バスの誰かでしょ? 当たったら教えて! 河野かな?」
「違うって。教えない! っていうか次の曲誰か予約いれなよ」
「夕姫ー、何か歌う? 一曲くらい入れたら?」
そう勧められた夕姫は、苦笑いしながら両手を胸の前で振る。
「私は大丈夫ですよ……みなさんのを聞いてる方が、好きですから」
「そっか。なんか冷たいの飲みたいねー」
「じゃあ……みなさん、飲み物頼みましょうか?」
夕姫が尋ねると、すかさず四方八方からオーダーが返ってきた。
「じゃあいちごミルクフロート!」
メロンソーダ! 麦茶! タピオカミルクティ!
つぎつぎ飛び交う注文を頭の中で繰り返しながら、夕姫は内線でオーダーを通す。友達の役に立てているかもしれないと思うと嬉しかった。
夕姫がせっせと飲み物を頼んでいる間に、友達が次々曲を入れていく。
すべての注文を終えた夕姫は、歌う人の邪魔にならないように、マラカスを小さく鳴らす。歌ったり踊ったりできなくても、楽しそうにしているみんなの隣にいたかった。
マイク片手に踊りだす友達を見て、目を細める。
みんなすごい。
バスケの試合中にも、同じようなことを思った。何かに夢中になっている人はすごい。背筋がしゃんと伸びていて、ふとした時に見せる笑顔に自信がにじんでいる。
夕姫はマラカスを振る手を止める。みんなは歌い続ける。マラカスの音が消えたことには誰も気づかない。
自分がどうしてここにいるのか、ふいにわからなくなることがあった。その不安はカラオケボックスの真ん中でも、コートの上にいるときでも、お構いなしに押し寄せる。
どうしてここにいるんだろう、は、禁句だ。心の中で一度でも、そう口走ると、友達やバスケのことを疑ってしまう。私は、本当にそれが好きなの? 友達といてちゃんと楽しいと思えてる? バスケを続けたい? ……疑念が飛び交う間、夕姫は体が硬直して、進むことも下がることもできなくなってしまう。
どうしてここに、の呪文を唱えずにすむように、夕姫は友達からの誘いには必ず乗るし、バスケ部の部員を置いて一人で先に帰るようなこともしない。もし少しでも距離を開けてしまうと、この輪の中にはもう戻ってこれないような予感がした。
「三年の夏が過ぎたら遊べなくなっちゃうんだから、今のうちに遊んでおかないとね!」
カラオケの帰り道、美砂たちがそう叫ぶのを聞きながら、夕姫は「そうですね」と頷いた。
自動車の音に混じって、ヒグラシが鳴いている。もうじき夏も終わりだ。
ちりん、とベルが鳴り、自転車に乗る高校生の二人組が夕姫たちを追い抜かしていった。
「あれってあの高校の制服じゃない? めっちゃかわいいねー!」
「そうだね、かわいいね〜」
「やっぱ高校は制服がかわいいとこ行きたいよね!」
友達が制服の話で盛り上がるのを聞きながら、夕姫はどんどん遠ざかっていく高校生二人の背中を見つめた。彼女らは、中学生の自分たちと二つ三つしか年は違わないはずなのに、圧倒的に大人に見えた。あと数年で、自分もああなれるんだろうか。
中学校生活が、瞬く間に過ぎ去ろうとしている。夕姫は中学生に憧れていた頃の気持ちを、今でも時折思い出す。
中学生になったら。そしたら好きな人ができたり、部活動に打ち込んで部員と苦楽を共にしたり、期末テストで慌てたり、友達との寄り道が楽しくて帰宅が遅くなり親に怒られたり、するんじゃないかな、と思っていた。
恋、部活、勉強、友達。小学生の時に思い描いていた理想の中学校生活に、自分は少しでも近づいているだろうか。
◇
放課後のチャイムがなった。校舎の一階では、部活動に励む生徒向けにパンの販売が行われていた。購買は混み合っていて、人気の菓子パンはいつも取り合いだ。
メロンパンを買いに来た夕姫は、人混みに押されてどんどん列の後ろに追いやられてしまう。前に進もうと四苦八苦しているうちに、目当てのメロンパンは残り二つになってしまった。
「さ、最後の一個だけ……でも……っ」
懸命に隙間から手を伸ばしたけれど、すんでのところで誰かに先を越されてしまった。
「メロンパン……」
メロンパンを諦めて列から外れた時、小さな指先が夕姫の背中を小突いた。
「これ、野崎さんのぶん。一生懸命買おうとしてたの、見えたから」
和香がメロンパンを一つ差し出した。もう片方の手には、クロワッサンの袋が見える。
「よかったら一緒に食べる? バスケ部の人たちのところに戻らないといけないなら、無理にとは言わないけど……」
「えっと……大丈夫ですよ。三十分までには戻らないと怒られるかもしれないですが…」
「それで怒られるの? 大変ね」
「そ、そんなことないですよ。心配かけちゃう私が悪いんです……」
「……そう。野崎さんがそれでいいならいいけど」
夕姫は和香に連れられて、中庭の古びたベンチに腰掛けた。クロワッサンをかじる和香の隣で、夕姫もメロンパンに口をつける。
「部活は調子どう?」
「調子ですか? 調子は……」
「楽しい?」
「……楽しいですよ」
「今、どうして答えに迷ったの?」
「……どうしてでしょう」
「部活、休んだほうがいいんじゃないかしら」
「ええ〜っ、どうしてですか?」
「あまり部活のこと考えたくないみたいだから」
「そんなこと……」
ない、と言いかけて夕姫は口をつぐんだ。部活動のことも友達のことも、問いただされると答えに困る。条件反射のように「バスケが好き」「友達といたい」と肯定的な言葉が口を突いて出るけれど、本心はどうかわからなかった。
バスケ部は、友達に誘われたからたまたま入っただけだ。友達の隣にいたいと願っているくせに、自分から誰かを誘ったことはない。どうしようもないくらい受け身な自分に気付くたび、夕姫はなんだか憂鬱になる。
「もっと自由になれたらいいわね。今の野崎さんは、なんだか息苦しそう」
和香の言葉が呼び水になって、練習試合の記憶が蘇った。体が強張って呼吸が止まったあの瞬間。自分に自信があれば、バスケが本当に好きだと確信が持てれば、友達のことを心から信頼していれば、もっとのびのびプレイできるんだろうか。
「……部活が辛くなった時に使えるおまじない、教えてあげましょうか」
和香が夕姫の顔を覗き込む。
「嬉しいですけど……私は、おまじないなんかじゃだめなんです。そういうのじゃ……どうにもならないんです」
「野崎さん?」
「自分に自信がないうちは、どんなことしたって……す、すみません。なんでもないです」
夕姫は慌てて謝り倒しながら、練習試合の前に教えて貰ったおまじないのことを思い出していた。
美砂が夕姫のために差し出してくれたメロンキャンディー。
『飴玉を食べたら緊張が解けるよ』
そんな優しいおまじないは、何の効力も発揮しなかった。甘えるばかりではいけない。強い女の子になりたいと願った。先週もそう願ったし、今日もまた同じことを願った。その事実に気がついて指先が震えた。
自分はこれからも、願ったり祈ったりすることしかできないんじゃないだろうか。本当に強くなれる日がくるとは到底思えない。
「……おまじないって、自信がないのをごまかすためにあると思うの。野崎さんはまじめだから、そうやってごまかすのが苦手なのね」
そう励ましてくれる和香に、夕姫は、ありがとうと伝えた。
「もうすぐお兄ちゃんの野球が始まるから、私はもう帰るわね。それじゃ、部活がんばって」
クロワッサンを食べ終えた和香は、踵を返し玄関へと向かった。夕姫は、お兄ちゃんの話をしている時の和香が好きだった。お兄ちゃんの話になると、和香は目をきらきらさせて、いつも冷めている口調もどこか熱っぽくなる。お兄ちゃんは、和香の強さの拠り所なんだと思う。
(私が、拠り所にしているところは……)
夕姫はメロンパンのビニール袋をくしゃりと丸めると、ゴミ箱に捨てた。もう、みんなのところに戻らないといけない時間だ。
◇
その日の部活は自主練だった。業者が入って、床やバスケットゴールの修理をするらしい。そのせいで、早く帰るよう先生から指導された。
「こんなに工事するくらいなら、いっそ新しい校舎立てればいいのにね」
部員同士で愚痴り合いながら、黙々と反復横飛びを繰り返す。
夕姫が通っている中学校は歴史が長く、校舎がとても古かった。授業が休みになる夏休み期間中に必ず修繕作業をしているけれど、それでは追いつかないらしい。
いつもより早く練習を切り上げると、更衣室で恋の話や学校の噂話に花を咲かせる。
「今日早めに終わるってわかってたらデートの約束してたんだけどなぁー」
と、のろけるチームメイトをみんなでからかっていたら、その話題が夕姫のところにまで飛び火した。
「夕姫は好きな人いないの?」
「え、好きな人ですか……?」
誰の顔も思い浮かばなかった。
好きな人……と、その単語を頭の中で反芻しながら、目をそらす。すると更衣室の鏡に映る自分と目があった。申し訳なさそうに肩を丸めている。その自分を見て、恋なんてとても考えられないと思った。自分に自信を持てないうちは、誰かを好きになることも好かれることも、ありえない。
「夕姫は好きな人いても自分から告白できなそー」
「うんうん。できないね、絶対できないよ夕姫は」
困惑したまま黙り込んでいる夕姫を見て、みんなが冷やかした。そこに美砂が助け舟を出す。
「自分からできる人の方が少なくない? だって、告白ってすごい怖いし不安だし、心臓壊れそうになるでしょ?」
ふーん、とみんなが相槌を打つ。会話が途切れ静まり返った瞬間、誰かがふと口を開いた。
「そういえばこないだ、こんな七不思議きいたよ。デマかもしれないけど」
夕姫の通う学校は、校舎に年季が入っているせいか、この手の七不思議や怪談話がいくつも存在する。ところどころきしむ廊下や、古い蛍光灯の明かりが、あやしげな話に真実味を与えるのに一役買っていた。
「どんな話?」
七不思議、と聞いて、占いやおまじないが好きな美砂の目が光った。
「知りたい?」
「なんでもったいぶるのー」
「こういうのはちょっと焦らしたほうがいいかなって」
「早く言わないと聞いてあげないよ」
部員からバッシングを受けて、彼女は、はーい、と素直に頷いた。
「うちの学校のプールにまつわる七不思議なんだけど」
「ああ、あのプール取り壊すらしいよね」
「ヒビが入ってて、危ないらしい」
七不思議の話を持ち出した彼女は、みんなの顔を見渡した後、声を潜めてこう言った。
「満月の夜、学校のプールを覗くと、好きな人の心の中が映るんだって」
それはまだ、バスケ部には広まっていない噂だった。聞いたことのない七不思議に、部員たちが耳を傾ける。
「それどういうこと?」
「告白しなくても、彼と両思いかどうか確かめられるってことじゃない?」
美砂は、へー、面白そう、と大して興味なさそうに答えた。
「本当に映るらしいよ? C組の女の子の間でちょっと流行ってるんだって。水面に好きな男の子と自分の親友がいちゃいちゃしてる場面が映って、トラウマになった子がいるって話聞いた」
「なにそれ、もうホラーだよ」
「夜の校舎っていうのが、すでにかなり怖いからね!」
手を叩いて笑いあう部員の中で、美砂だけがどこか神妙な面持ちで、自分のつま先を見つめていた。
夕暮れ時の空の隅に、白い月がぼんやりと浮かんでいた。ちょうど橙色と群青色が混ざり合っている天空に一番星が見える。
部活を終えて帰路についた夕姫は、だんだん日が暮れるのが早くなっていることに気づいた。
「さっきの七不思議だけど、面白そうじゃない?」
隣を歩いていた美砂が身を乗り出す。
「みなさんの前では、あまり興味なさそうにしてたのに……?」
「だって興味ある顔してたら『美砂の好きな人誰?』ってまた問い詰められるじゃん。夕姫はそういうこと聞かないから好き」
「あっ、ありがとうございます」
夕姫は頬を赤らめた。自分もあっけらかんと友達に「好き」と言えるようになりたいと思った。
「夕姫、今度やってみようよ。プールが取り壊される前に」
「ええっ」
「お願い、付き合って。どうしても試してみたいんだけど、夜のプールに一人は怖いから」
「うーん……」
家を抜け出す時は親になんて言い訳しよう、夜道を歩いてて怖い人に出会ったらどうしよう、プールのそばにいるところを用務員のおじさんに見つかったら……。胸に押し寄せた様々な不安を、美砂の一言がかき消した。
「お願い!」
自分を好いてくれる友達の頼みを、断ることはできなかった。
「ちょっと試すだけだから。夏の思い出だと思ってつきあってよー!」
美砂からそうだめ押しされて、夕姫はおずおずと返事を返す。
「わ、わかりました」
喜ぶ美砂を横目に見ながら、夕姫は先ほど聞いた七不思議について思いを巡らせた。
学校のプールに、好きな人の心の中が映る。
きっとただの噂話に違いないけれど。もし、好きな人がいない場合は、水面に何が映るんだろう。
◇
プールの水は張られたままで、ほのかに塩素のにおいがした。夕姫と美砂は靴を履いたままプールサイドを歩く。
「きちゃったね」
いたずらっぽく笑う美砂につられて、夕姫も「きちゃいました……」と笑った。
「親になんて言ったの?」
「え、ええと……宿題のノートを友達の家に忘れたから、すぐ取って帰ってくるって」
「常套句だね」
小さな足音が響く。夜の学校は、どこかよそよそしい。慣れ親しんでいるはずの場所が、他人の庭のように感じた。
「もし、見つかったら……怒られちゃいますね」
「それもまた思い出になるじゃん」
美砂は夕姫の手を引っ張って、プールに近づいた。
夜空を映す真っ黒な水面は、冷たい夜風に吹かれて小さな波紋を起こす。雲に隠れていた月が顔をだし、水面に光の破片が散らばる。
月の光を受けて明るくなった水面は、あらゆるものを映す鏡のように光っていた。
「覗いてみようよ」
美砂に誘われて、夕姫もプールの縁に膝をつき、前かがみになる。
「何か見える? 真っ黒だよ」
目を凝らす美砂の隣で、夕姫も水面を見つめた。
黒い水面は、どこまでも深い穴につながっていそうで底知れない。水深一.二mしかないプールだとわかっていても、落ちてしまえば光の届かないところまで溺れてしまいそうだ。
その水面に、怯えている自分の顔が映る。
自分の顔しか映らないんじゃ、ただの鏡と同じだ。やっぱり七不思議なんて誰かの作り話なんだと、夕姫が納得した時だった。
水面を切り裂くように、光が走った。きっと流れ星だ。月だけじゃなく、夜空の星まで映りこんでいるらしい。夕姫は目を見張った。水面に小さな波が立ち、沸騰しかけたお湯のように、細やかな泡が浮かんでは消えた。
滑らかになった水面が大きなスクリーンに変わる。そこにはっきりと映し出されたのは、凛と背筋を伸ばしている女性の背中だった。すらりと背が高く、長い金色の髪を揺らしながら、胸を張って歩いている。
(誰?)
心の中で呼びかけると、水面に映る彼女がゆっくりと振り返った。見覚えのある横顔に、はっとする。
(わ、私……?)
水面に映る自分は、どこか遠くの一点を見据えていた。何を見つめているんだろう、どうして自信ありげに見えるんだろう。夕姫は彼女の姿をじっと見つめる。
彼女は意志の強そうな目で、グラウンドに仁王立ちしていた。片手にはバットを持っている。
話しかけてみたい、と思った時、水面に映る彼女と目があった。これは、私の知らない、私の顔。夕姫が生唾を飲み込むと、水の中にいる彼女が優しく微笑みかけた。柔らかそうな唇がゆっくり動く。
私たちなら……きっと、勝てるよ。
勝てる、ってどういうこと? 何と戦ってるの? 夕姫が身を乗り出した時、生暖かい風が頬を撫でた。どこからか飛んできた鳥の羽が水面に落ち、波紋を起こした。水面が揺れた瞬間、蜃気楼のように映像が遠のいていく。
もう少し見ていたいのに、と焦った瞬間、美砂が夕姫の腕を摑んだ。
「あっ」
「夕姫ー。あんまり前かがみになると、プールに落ちちゃうよ」
「そう、ですね……」
プールの水面に目を向けた。そこには、大きな月が映りこみ、白い羽が小舟のように流れているだけだった。
「やっぱり、何も映らなかったね」
美砂が両腕を上げて体を伸ばしながら、気だるそうにそう言った。
「え?」
「でも、まあ楽しかった。いろんな占いとかおまじないためしてると、恋煩いを忘れられるからいいの。今日は付き合ってくれてありがとう」
「いえ……こちらこそ、ありがとうございました」
帰ろうか、という美砂の言葉に頷いてプールサイドを後にして、美砂と別れる。グラウンドのフェンスを飛び越えた夕姫は、足を止めた。
満月の夜、学校のプールに好きな人の心の中が映る。その七不思議は、ちょっと間違っているのかもしれない。
夕姫は数分前に自分が見たものを思い浮かべる。あれは、自分の理想の姿か、それとも将来の自分の姿か。何かと戦っているようだった。
夜道を歩いていた夕姫は、ぐっと自分の背筋を伸ばしてみた。胸を張って歩こうとすると、腹筋に力が入る。背中をまっすぐにして歩くと、自然と大股になり、手足がどんどん前に出た。
慣れない歩き方をしたせいか、太ももに余計な力が入る。夕姫は立ち止まり、夜空を見上げた。
自分に自信を持てたら、といつもの癖でそう願った。それから、願うばかりじゃだめだから、と前を見据える。
水面に映った自分の姿を真似て歩く。たとえ幻だったとしても、堂々と歩く自分の姿は、なんだかちょっとかっこよかった。
夕姫は足早に自宅へ向かう。満月が夕姫の行く道を照らす。その背中を、電柱に止まる白い小鳥が見守っていた。