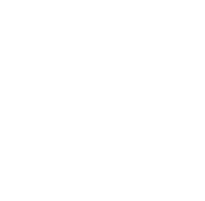第12話 阿佐田 あおい「博打猫」
――尻尾のない猫についていってはいけないよ。
そう言うと、じいちゃんは皺の刻まれた手で、湯飲みを握った。キツネの絵が描かれた古い湯飲みだ。
どうしてなのだ? あおいが尋ねると、じいちゃんは白い眉をぴくりとさせ、不敵に笑う。
――尻尾のない猫は、博打猫なのさ。尻尾がないのは、博打に負けて尻尾をとられたせいなのさ。ようするに博打狂いなんだ。
なーんだ、それじゃ、じいちゃんの仲間なのだ。
するとじいちゃんは大口を開けて笑った。銀色の糸切り歯が光る。
尻尾のない猫についていくとどうなるのだ? あおいが尋ねると、じいちゃんは、聞きたいかい? ともったいぶって答えた。
聞きたいのだ! と威勢良く返すあおいに向かって、じいちゃんは拳を突き出した。握った拳をゆっくり開くと、そこにはサイコロが三つ。
――これでわしに勝ったら、教えてやろう。
◇
「じいちゃんは強すぎるのだ……」
チンチロリンで負けたあおいは、縁側でごろりと横になった。じいちゃんは、はっはっは、と豪快に笑う。夏休みがくると毎年、あおいはじいちゃんの家に遊びにいく。そこで博打を教えてもらうのを楽しみにしていた。けれど、なかなかじいちゃんに勝つことはできない。
「おじいちゃん、少し手加減してあげたらどうです」
「博打に手加減もなにもあるかい! 賭博場では女子供もみな平等じゃ!」
じいちゃんは語気を強めると、ばあちゃんが持ってきてくれた新しい緑茶に手をかざした。温かい緑茶の湯気で、指先を温める。夏場だろうと、博打の時はじいちゃんは必ず温かいお茶を口にした。指先が冷えると勘が鈍る、というのが、博打後のじいちゃんの口癖だった。
「尻尾がない猫の秘密、知りたいのだー」
悔しがって足をじたばたさせていると、あおいのお腹に猫が飛び乗ってきた。
にゃあ。茶色いブチのある猫だ。ブチ猫はあおいを小馬鹿にするように、にゃあ、ともうひと鳴き鳴いた。猫を撫でようとすると、ブチ猫は長い尻尾を揺らしながら、さっとあおいを踏みつけて軒先へ逃げていく。
「ばあちゃん、猫にお水あげてもいい?」
「いいよ。この暑さじゃ、猫も喉が渇くでしょうに」
ばあちゃんはあおいが幼稚園の頃に使っていた小皿に水をたっぷりいれてくれた。それを庭に置くと、茶色いブチ猫だけでなく、白猫や灰色猫、黒猫たちが集まってくる。
猫たちはちょこちょこと水を飲んでは、軒先で寝転んだり、庭にある木に登ろうとしたりして自由気ままに過ごしていた。あおいは、一人遊びに興じる猫たちを見ているのが好きだった。猫たちはいつもあおいのそばにいるけれど、決して懐きすぎることはない。餌をやる時にはくるけれど、餌をもらうために媚びたりしない。頼るところは誰かに頼りながらも、あくまでマイペースに生きる。それが猫道。ああっ、トンガリお耳にぱっちりお目目、あんなにキュートな猫さんは、実はとても強い生き物なのだ〜っ。あおいは甘いため息をつきながら猫たちを眺めた。そして、庭に生えていたエノコログサをちぎる。猫じゃらしとも呼ばれる雑草だ。
猫と遊ぼうとした時、ばあちゃんがあおいを呼んだ。
「あおい、ひいおじいちゃんたちにもお水あげてくれるかい」
「了解なのだ」
あおいは猫じゃらしを庭先に捨てると、台所へ走った。金色の器にペットボトルの水を注ぐ。水道水を一晩月の光に当てて清めたお水だ。こぼれないように気をつけながら、つま先立ちで畳の縁をまたぐ。
「わしの博打好きは、この人譲りかもしれんの」
じいちゃんは仏壇を一瞥した。じいちゃんより強い人がいるなんて想像できない。
仏壇に水を供えると、あおいは正座して両手を合わせた。後ろでばあちゃんも膝をつき、あおいと一緒に手を合わせる。
欅で作られた橙色の仏壇には、モノクロの写真が飾られている。あおいが生まれる前に亡くなってしまったひいじいちゃんとひいばあちゃんの写真だ。ばあちゃんとじいちゃんの家に遊びに来た時に、仏壇の写真を通してしか会ったことはないけれど、きっと優しい人だったんだろうと思う。モノクロの写真に写る二人は、とっても幸せそうだ。
「ひいじいちゃん、ひいばあちゃん。今日もとてもいい天気なのだ」
写真に向かって笑いかける。できることなら、ひいじいちゃん、ひいばあちゃんと、一度くらい直接話してみたかった。
「いい天気、かねぇ……?」
後ろのばあちゃんが首をかしげる。ばあちゃんは軒先まで歩くと、手のひらを庇にして目を守りながら、太陽を見上げた。空は雲ひとつない快晴だ。けれど、どこからともなく、銀色の糸のような細い雨が降り注いでいる。明るい地面を、ちくちくと透明な雨つぶが濡らしていた。
軒先で猫の相手をしていたじいちゃんがつぶやく。
「キツネの嫁入りだね、こりゃ」
「あおい。天気雨だよ」
じいちゃんとばあちゃんの指摘を受け、あおいは仏壇にもう一度手を合わせる。
「……修正するのだ。ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん。今日は天気雨なのだ。キツネの嫁入りなのだ」
天気雨が降り始めると、庭先や軒で遊んでいた猫が蜘蛛の子を散らすようにどこかへ消えた。あおいが猫の鳴き声ひとつしない庭先を見渡し「猫さんたちどこいったのだ?」と尋ねると、じいちゃんは肩をすくめる。
「キツネの嫁入りを祝いにいったのかもしれないねえ」
と、ばあちゃんは目尻に皺を寄せて微笑んだ後、
「ところであおい、学校の宿題は大丈夫なの? 夏休みの宿題、たくさんあるんでしょ?」
と尋ねた。
「かんぺきなのだ! 夏休みをあそびたおすために、とーってもがんばったのだ!」
「それならよかった。今日はどこか遊びに行かないの?」
「ふにゃ〜、今日は雨だから、やっぱり家にいることにするのだ」
「よし! それなら次は花札でもやるか!」
「おじいちゃん、そんなギャンブルばっかり教えないでくださいよ。今日はみんなで双六しましょ。商店街で買ってきた落雁とおせんべいがあるから、それでもつまみながら、ね」
「にゃー! 双六なら負けないのだ!」
◇
昼間降っていた天気雨は、深夜豪雨に変わった。大きな雨粒が屋根を激しく叩く。パジャマ姿のあおいは、眠れないのだ……とつぶやきながら、手足を丸め、布団の中に潜る。
にゃあ。にゃあ。にゃあ。
庭先から雨音に混じって、猫の鳴き声がした。猫の声を聞き、あおいの目がぱっと開く。
もしかして、猫さんは雨宿りする場所を探して鳴いているかもしれないのだ。
猫が心配になったあおいは、傘を二本もって長靴を履き庭に出た。一本は自分の傘で、もう一本はじいちゃんのものだ。
「どこにいるのだー?」
雨の中、あおいは猫に呼びかける。にゃあ。にゃあ。にゃあ。大声で泣く猫の声は聞こえるのに、なかなか姿は見えない。
「おーい」
にゃあ。にゃあ。にゃあ。
庭を歩き回ると、大きなフキの葉の下で丸くなっている猫を見つけた。
「にゃっ!?」
ようやく見つけた猫の姿を見て、あおいはぎょっと後ずさる。丸くなる猫の足元が、ほのかに赤く染まっていた。尻尾にはちぎられたような傷があり、まだ血がにじんでいる。よく家に遊びに来る茶色いブチのある猫だ。昼間見たときには、確かにその猫には尻尾があった。いつの間に、誰がこんなことをしたのだろう。
「手当てしてあげるから、おいで。おいで」
手を伸ばすと、猫はシャーーッ! と唸り声をあげた。鋭い目であおいを睨む。
「こわくないのだ、だいじょうぶ、だいじょうぶ。だからおいでなのだ」
猫はあおいに背を向けると、フキの下に潜っていく。待つのだ、とあおいは膝をついて猫をおいかけた。庭の隅の石壁には子どもが一人通れるほどの小さな穴が空いている。ブチ猫はそこを抜けていった。あおいも、迷わず猫の背をおいかける。
穴の中に入ると、うるさい雨音がぴたりと止んだ。
石壁の厚さは、せいぜい十数センチくらいしかない。壁をくぐればすぐに隣の空き地に続いているはずだった。けれど、数歩分這っても壁を抜けることはない。まるで土管の中を通っているようだった。妙に長いのだ、とあおいが不思議に思っていると、向こうから光が見えた。
ようやく這い出ると、夜空には大きな満月が照っていた。空き地の中心には芝居小屋のような建物がたっている。小屋の中心には相撲の土俵のように盛り上がった舞台があり、キツネたちがその舞台の上で一升瓶に入った酒をあおっていた。
キツネ……?
あおいが目をこすっていると、
「人間を連れてきた」
茶色いブチのある猫がしゃべった。
「お前、しゃべれたのか!?」
ブチ猫は、ぷいっと顔を背け、颯爽とした足取りで猫の仲間が待つ観客席へと戻っていく。ブチ猫を取り囲む猫たちは、全員尻尾がなかった。
「おお、ほんとうだ。人間だなぁ。これはまた、小さな小さな女の子じゃないか」
ほっそりしたキツネがあおいの前に立つ。そのキツネはチョッキを羽織っていて、人間のように二本足で歩いた。
「お嬢さん、これのルールは知ってるかい?」
キツネは毛むくじゃらの手をずいと突き出す。茶色い手のひらの上に茶碗が現れた。その中には、小さなサイコロが三つある。
「チンチロリン……?」
「ほお。知っているのかい。なら、少しは楽しめそうだ」
キツネはにやりと口角をあげて不敵な笑みを浮かべた。
「それより、あの猫さんの手当てをさせて欲しいのだ」
「それよりお嬢さん、自分の心配をした方がいいんじゃないのかい?」
どういうことなのだ? あおいは辺りを見回した。あおいが通り抜けてきた壁は消えており、振り返ればすぐそこにあるはずの家がどこにも見当たらない。
「チンチロリンのルールは知ってるらしいが、ここでのルールは知らないようだね」
ずい、とキツネがあおいに顔を近づける。
「ここでのルール……? なんなのだ」
「チンチロリンで俺に勝つまで、ここからは帰れないのさ」
「どういうことなのだ?」
「そのままの意味だよ。俺に勝つまで、帰れない。その猫の手当てだってできない。でも、これはチャンスでもあるんだよ。もしお嬢さん、あなたが俺に勝ったなら、お嬢さんが望むものをあげよう」
「望むもの……?」
望むもの。仏壇の写真でしかみたことのない、ひいおばあちゃんとひいおじいちゃんの顔が瞬時に頭をよぎっては、消えた。本当に望むもの。それは確かにあるような気もするし、そんなものは何もないような気もした。
「そう。なんでもいいよ。どんなことだって。お嬢さんが本当に望むものをいっていい。これは特別な賭博だからね。お嬢さんが勝ったならそれなりの報酬を手にできるのさ。あの猫の尻尾も元に戻してあげるし、お嬢さんを柔らかいお布団の中に帰してあげよう」
「でも、あおいは賭けるものをなにも持ってないのだ……」
あおいは口をつぐんだ。もしこれが本当の賭博なら、あおいも何か賭けなければいけない。目の前の相手はじいちゃんと違って、「肩たたき券」や「お茶くみ券」では手を打ってくれなそうだ。
「いやいや、お嬢さん。賭けるものをもっていない人間なんて、いないのさ。あなたが負けたら、あなたの大事なものを一つずつ、もらっていくよ」
「大事なもの?」
あおいは向こうで丸くなっている尻尾のない猫たちの方へ目をやる。自分が本当に望んでいるものが何か、まだわからない。ただ、今この瞬間は、あの猫を助けたいと思った。
「どうする?」
キツネが問いかける。
博打に勝つまで帰れない。勝てば、猫の尻尾も元に戻る。どのみち、この勝負を避けて通ることはできなそうだ。
「……その賭け、乗ったのだ」
あおいはいつもじいちゃんがやるように、自分の二の腕をぱん、と叩いた。キツネはチェシャ猫のようにニタァ、と笑う。
「いいね。威勢がいい子は好きだよ、俺は」
はじまるよ、とキツネが声を上げる。すると、土俵で酒盛りをしていたキツネたちは急に酔いが覚めたようにきびきびと働き始める。宴会場は、あっという間に賭博場に早変わりだ。
おいで、とキツネに呼ばれて土俵に上がる。その舞台を囲むようにぐるりと座布団が敷いてあり、百匹あまりのキツネがあぐらをかいて座っていた。本物のキツネだけではなく、木彫りのキツネや瀬戸物で作られたキツネも混じって座布団の上に飾られている。中には、白無垢と羽二重の着物に身を包んだキツネもいる。この賭博は、祝いの席の後の、見世物なんだろうか。キツネたちの視線があおいに集まる。興味津々、といった様子だ。賭博中の私語は禁止なのか、これだけの数がいるのに不思議と会場は静かだった。
ちりん。
ネズミの頭蓋骨でできた風鈴が寂しげな音を奏でる。舞台の奥にある床の間のような場所には、キツネの毛皮が掛け軸のように飾られていて、その前では老いたキツネのばばあが出刃包丁の刃こぼれを見ていた。
「勝負なのだ」
あおいが威勢良く土俵の上に座る。まあまあそう慌てなさんな、と諌めながら、キツネはちょっこりとあぐらをかく。
「そうさなぁ、まずは練習がてら。その傘を賭けてもらおうか」
それはじいちゃんが大事にしてる傘なのに、とあおいはたじろいだ。
「こっちの傘ではだめなのだ?」
あおいは自分の傘を賭けに出そうとしたけれど、キツネは大きく首を振る。
「それじゃ小さすぎるよ。ちょうどいい番傘が欲しいなと思ってたところでね。お嬢ちゃんは何が欲しい? いってごらん」
「猫さんのしっぽを返して欲しいのだ」
「その傘と猫の尻尾じゃ釣り合わないような気がするけど、まあいいよ。最初だからね。いいだろう。乗った乗った」
そういうと、キツネはサイコロを茶碗の中に入れた。
一回目の勝負はあっさりとついてしまった。
キツネがふった賽の目を見て、観客のキツネは座布団を放り上げて笑った。一回目の勝負、あおいが得た点数は二点。キツネは三点だった。
「お嬢ちゃんの目は、三・三・二かい。おしかったね。じゃあ、これはいただくよ」
目に見えない蜘蛛の糸にでも引かれるように、足元にあったじいちゃんの傘が宙に浮いた。それはゆらゆらと空中を泳いで、奥で出刃包丁を研いでいたキツネばばあの手の中に落ちる。
無事、傘が自分の陣営側に渡ったのを見たキツネは、仕切り直し、とでも言いたげに両手を叩いた。
「さて、次はどうしようか」
「……猫の尻尾と、じいちゃんの傘を取り返すのだ」
勝たなければ帰れない。それなら、後へは引けなかった。
「ふむふむ、なるほどね。それじゃあ、俺は何をもらおうか。そうだなぁ……猫のしっぽと、この傘。その二つと釣り合いそうなもの……。ああ、片付けたばかりの夏休みの宿題なんてどうだい?」
「乗ったのだ」
あおいのこめかみのあたりを、嫌な汗がつう、っと伝った。勝たなければ、じいちゃんに怒られる。猫の尻尾とじいちゃんの傘だけでも。
その賭けの結果も、同じようにあおいの負けで終わった。キツネがすっと手を振ると、そこに片付けたばかりのドリルやノートが現れる。キツネがそのドリルやノートを逆さまにして振ると、あおいが苦労して解いた回答が消しゴムのカスのようにはらはらと落ちていく。キツネの子供がページから落ちた回答を素早く拾い集めて去って行った。
「いただいたよ」
キツネが、ドリルとノートを地面に捨てた。ページがめくれる。埋めたばかりの解答欄はすべて空欄に、ノートは白紙に戻ってしまった。
「それじゃ、次は何を賭けようか。お嬢ちゃんが欲しいものは、猫の尻尾、傘、終わった宿題、でいいかい?」
「最低でも、とられたものは、ぜんぶ取り返して帰るのだ」
「いいね。そうこなくっちゃ。じゃあ俺は何をもらおうかなぁ」
キツネは丸い顎を撫でながら、悩ましげにあおいを見つめる。
キツネの博打の強さは尋常ではなく、とてもあおいが太刀打ちできそうになかった。もしかして何かイカサマを? あおいはじっとキツネの手元を見つめたけれど、もし仮にイカサマをしていたとしても、見破れそうにない。証拠がないのに「イカサマだ」と告発するのはルール違反だ。
その後の勝負も、あおいの惨敗だった。
誕生日にもらったくまのぬいぐるみ。いつも食事の時に使っている猫柄の茶碗。お気に入りの枕。友達とおそろいの色鉛筆。じいちゃんに褒められた絵。お年玉を貯めている猫の貯金箱。ばあちゃんの作るよもぎ団子。
あおいが大事にしていたものが、どんどんキツネに取られてしまう。戦利品を積んである奥の間は、あおいの所有物でいっぱいになっていた。
「もうちょっとがんばってくれないと困るよ、お嬢さん。賭け事はもっとスリリングでなくちゃいけないからね」
あおいのものをひとしきり取り上げたキツネは、わざとらしくため息をついた。
「……つぎは、ぜったい……」
あおいはパジャマの袖で、てのひらにかいた汗をぬぐった。緊張と不安で、賽を取ろうとする手が滑る。
「つぎこそは、ね。そうなると、いいね。うーん、次の賭け物はどうしようか。だんだん、欲しいものがなくなってきちゃったんだよねぇ」
「それは困るのだ。あおいは、ぜんぶとり返したいのだ」
「うーん……どうしようねえ。……ああ、そうだ。じゃあこれを賭けてもらうよ」
キツネはもじゃもじゃの人差し指であおいの額を小突いた。その瞬間、あおいの頭に笑っている両親の顔が浮かんだ。あおい、と優しく自分の名を呼ぶ声がする、あおいとアイスを半分こして笑う父親と、お腹を壊すわよ、と怒る母親の顔。あたたかい思い出が走馬灯のように駆け抜けた。
キツネの指が離れる。我に返ったあおいは、床に片手をついた。
「両親との思い出を賭けてもらうよ。いいね?」
「よくないのだ! さっきまで賭けていたものと、ぜんぜん次元がちがうのだ」
「さっきまでのは、まだまだ。ほんの小手調べだからねえ。それに、もっと大事なものを賭けたほうがお嬢さんも本気になれるんじゃないのかい? 宿題や石ころを賭けるんじゃ、お嬢さんは全然その気になれないみたいだからねえ」
「でっ、でも……! それは……」
「いいんだよ。降りても。ただねえ、そうしたらお嬢さんが手放したものは永遠に返ってこないよ」
あおいは下唇を噛んだ。賭けたくない。これだけは、賭けのアイテムなんかにしてしまいたくない。
「他のもので手を打ってほしいのだ」
「……仕方ないね。お嬢さんがそんなに言うんだったらね、じゃあ、そうだね。特別に他のもので勝負してあげるよ。両親との記憶以外のものだったらいいんだね? 乗ったね?」
「乗ったのだ」
「よしきた。じゃあお嬢さんのおじいちゃんとおばあちゃんをもらおう」
「ええっ」
あおいの手から、茶碗とサイコロが落ちる。嘘なのだ、やめるのだ、とわめいたけれど、キツネは首を縦に振らない。
「これでも譲歩してあげたんだけどなぁ。気にくわないのかい? それは残念だ。でも、もう勝負は始まっているからね。あとは賽を振るしかないよ。いい目が出るよう祈ることだね」
「そんな……」
めまいがした。悪い夢ならもう覚めてほしい、と目をこすってみる。強くこすりすぎて、涙がにじむ。ああ、もうやるしかない、やるしかないんだ。怯えても後悔しても仕方がない。残された選択肢は一つしかなかった。何もかも元どおりにして家に帰るには、勝つしかないのだ。
いまこそ、ここでこそ。じいちゃんに鍛えられた博打の腕前を見せる時だ。
「あおいが先に振るのだ」
あおいは落とした茶碗とサイコロを拾う。茶碗の中にサイコロを入れて回すと、地面に置く。
「さて、どんな目がでるだろうね?」
会場にいるキツネたちがどよめく。あおいがゆっくり、出目を確認しようとした時だった。
「夜更かしするとお母さんに怒られるぞ。何時だと思ってる」
大きな手があおいの頭を撫でた。そのてのひらが、あおいのまぶたを静かに覆い隠す。
「もう寝ろ」
じいちゃんの声だろうか。それにしては、妙に若々しいように聞こえる。
「じいちゃん……なのだ……?」
「だまって、羊の数でも数えてな」
あおいは肩の力が抜けていくのを感じた。まぶたに触れていた手が離れた時、うすぼんやりと見えた助っ人の顔は、遺影でしかみたことのないひいじいちゃんによく似ていた。
心配かけて、ごめん、ごめんなのだ。
謝ろう、と思っていたあおいの口からこぼれたのは、静かな寝息だった。優しい声を聞いた途端、張り詰めていた緊張の糸が切れ、あおいはその場に横になる。
キツネがあおいを罵った。
「だいたい、猫を助けようなんてことするからいけないのさ」
「うちの可愛い娘に手を出すとはね、この化狐。わしは、博打ってもんは強奪の手段じゃなく、夢を買う手段だと思っとるんだが。まあ、たまにはこういう博打も燃えるわい」
遠くなっていく意識の中で、ひいじいちゃんか、じいちゃんか……の小さな背中がやけに頼もしく見えた。
◇
にゃあ、と猫の鳴く声がした。
まぶたに明かりが落ちる。あおいは眩しくて目をこする。視界に飛び込んできたのは、天井の茶色い梁だった。布団から飛び起きる。くまのぬいぐるみ。色鉛筆。猫の貯金箱に、柔らかい枕。いつもどおりの部屋だ。学習机の上にある夏休みの宿題をめくる。ドリルもノートも、きちんと終わらせてあった。
キツネに奪われたはずのものが、すべて元に戻っている。
「あおいー、起きたかい。朝ごはんだよー」
ばあちゃんの声がする。あおいは、今行くのだー! と答えて食卓に向かう。よもぎの良いにおいがする。ばあちゃんの得意料理、よもぎ餅だ。長机にはよもぎ餅の他に、卯の花と目玉焼きが並んでいる。
じいちゃんは食卓に座り、温かい緑茶を飲んでいた。
「あおい、おはよう」
無愛想にお茶をすすっているじいちゃんをみたあおいは「じいちゃん!」と声を高ぶらせた。
「朝から元気じゃな、あおいは」
じいちゃんは一息つくと、また湯飲みを口元に運んだ。蛇の絵が描いてある、見慣れない湯飲みだ。お気に入りの湯飲みはどうしたのだろう。キツネの絵が描いてある、古くて茶渋がついたあの湯飲みは。
「あれ、じいちゃん。いつも使ってる湯飲みはどうしたのだ? 新しいのに変わってるのだ」
「ああ、あれはな、今朝割れたから、庭に埋めたよ」
じいちゃんは庭に生えている梅の木の根元を指差した。掘り返したような跡があり、そこだけ土が黒く湿っていた。
「掘り起こすんじゃないよ」
庭を見つめていたあおいに、じいちゃんが釘を刺した。わけがわからなかったけれど、なんとなく、あおいはこくりと頷いた。
朝食の支度をおえたばあちゃんが、割烹着を脱ぎながらあおいの隣に座る。
「昨日はすごい雨だったね。ちゃんと眠れたかい、あおい」
「う〜、すこしだけ、ねぶそくなのだ」
ばあちゃんは顔をくしゃりとさせて微笑んだ。
「そうかい。とりあえず朝ごはんにしようか」
三人で手を合わせて、いただきます、をする。仏壇には新しい水が供えられており、遺影に映るひいじいちゃんとひいばあちゃんはいつもと変わらず穏やかな笑みを浮かべていた。
朝食を食べた後、じいちゃんに昨晩のことを聞いたけれど「なんだ、わしと勝負したいのか?」とはぐらかされるばっかりで、肝心のことは何も答えてくれなかった。化狐が、猫の尻尾が、とあおいが口走っても、じいちゃんはまるで相手にしてくれない。
日が暮れかかった頃に、あおいはこっそり一人で庭に出た。昨日の夜通ったはずの、壁の穴を探す。けれど茂みの中には、猫が一匹通れるような穴が空いているだけで、あおいがくぐれるようなすきまはどこにもなかった。
昨日の出来事が夢じゃなかったことの証拠は、ないんだろうか。あおいは地面に座り込む。すると足元のあたりから、小さな物音がした。梅の木のあたりだ。
あおいは梅の木の根元に手をついて、じいちゃんが湯飲みを埋めたという場所に耳を近づける。すると地面のずっと奥から、からん、とサイコロの転がるような音が聞こえた。その音はだんだんか細くなり、やがてあおいの耳では聞こえないほど小さくなっていく。
もしかしたら、じいちゃんは湯飲みの中にあのキツネをとじ込めて、一緒に埋めてしまったのかもしれない、とあおいは思った。そしてキツネたちは今でも、キツネ同士で賭博を続けているのかもしれない。
立ち上がり、膝についた土を払っていると、一匹の猫と目があった。
塀の上に、茶色いブチのある猫が座っている。ブチ猫は長い尻尾を揺らしながら、草むらの中に消えていった。